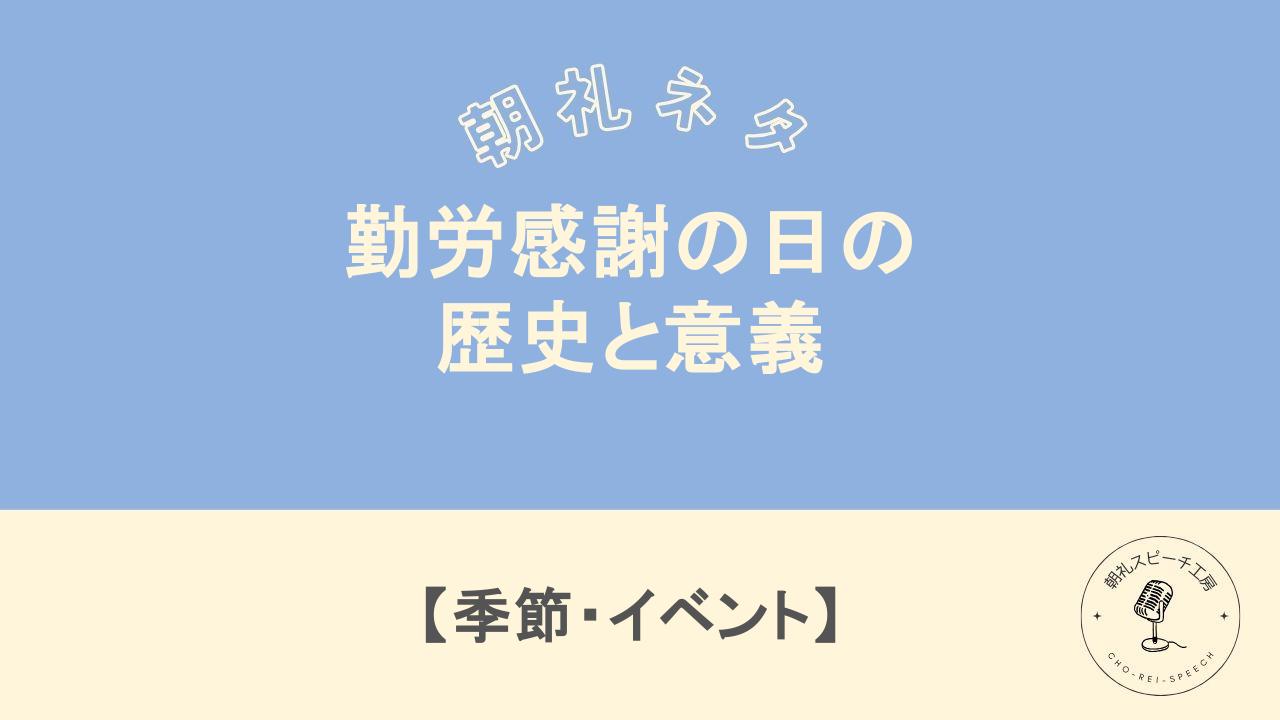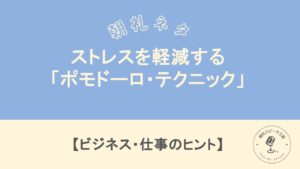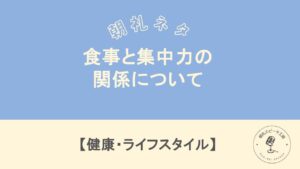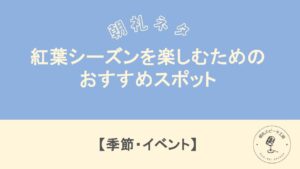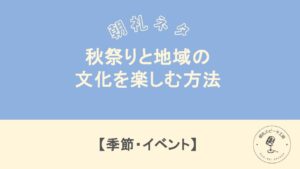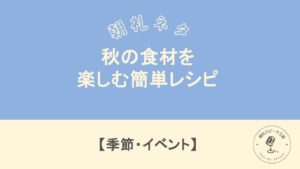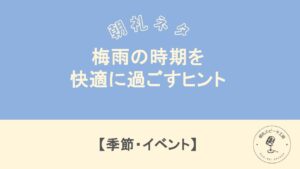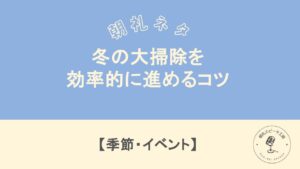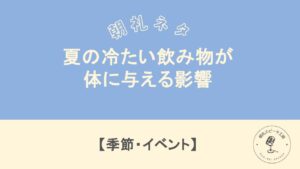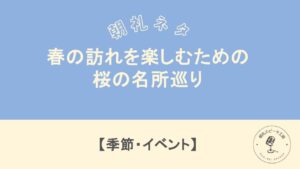目次
勤労感謝の日の歴史と意義
おはようございます。
11月23日は「勤労感謝の日」です。この日が祝日である理由や、どのような意義が込められているのかを改めて考えたことはありますか?今日は、勤労感謝の日の歴史とその意義について3つのポイントでお話しします。
1. 起源は「新嘗祭」
勤労感謝の日の起源は、古代から行われていた「新嘗祭(にいなめさい)」という宮中行事にあります。この行事では、その年の収穫に感謝し、自然の恵みや人々の労働をたたえるものでした。新嘗祭は天皇が神々に新しい穀物を捧げる儀式で、日本の農業社会に根ざした重要な文化行事でした。
2. 現代の勤労感謝の日への変化
1948年に制定された祝日法により、新嘗祭をもとにした「勤労感謝の日」が誕生しました。この日には、「勤労をたっとび、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう」という現代的な意義が込められています。農業だけでなく、すべての職業に従事する人々の努力に感謝する日として広がりました。
3. 感謝を通じて得られるつながり
勤労感謝の日は、普段の忙しい日常から少し離れ、自分や他人の働きに対して感謝を伝える機会です。この感謝の気持ちは、家庭や職場、地域社会とのつながりをより深めるきっかけにもなります。また、感謝することで、自分の働き方や他者への思いやりについても改めて考えることができます。
勤労感謝の日は、歴史ある「新嘗祭」に由来し、現代ではあらゆる勤労に感謝する日となっています。私たち一人ひとりの努力と支え合いによって、社会が成り立っていることを改めて認識する日です。
今日もお互いの働きに感謝しつつ、明日への活力を蓄える一日にしましょう!
以上です。ありがとうございました。