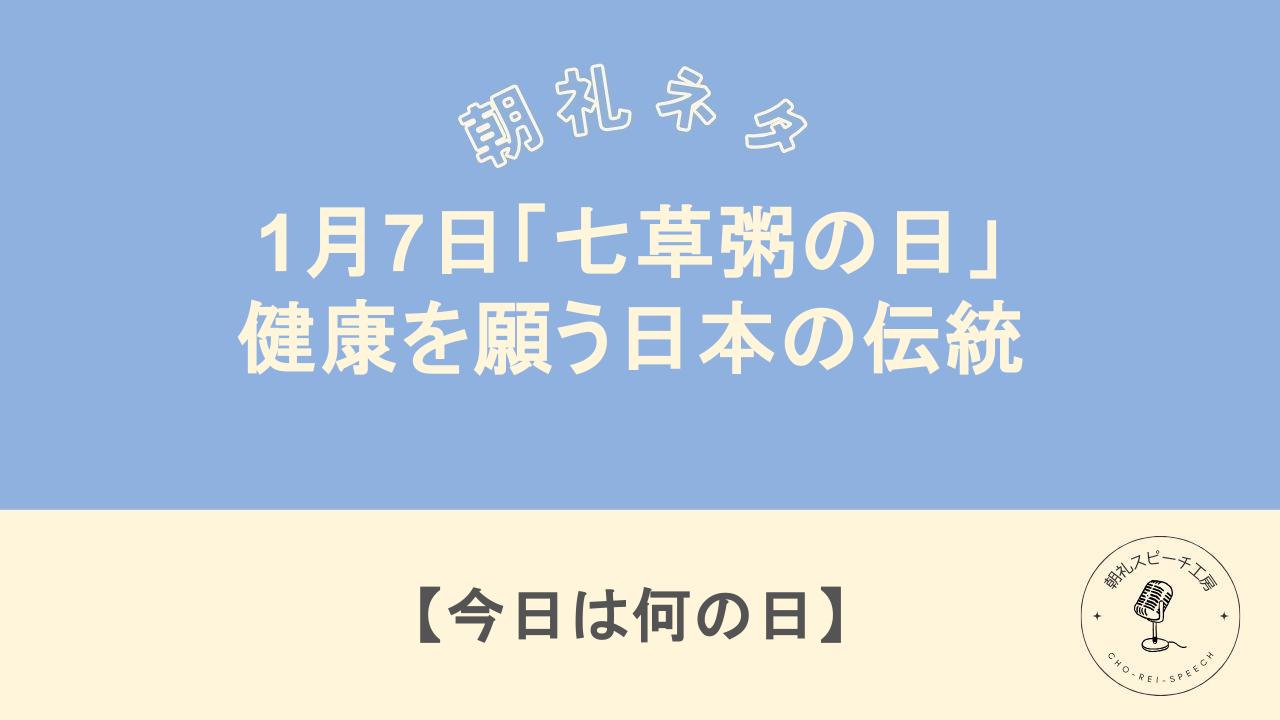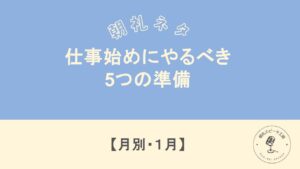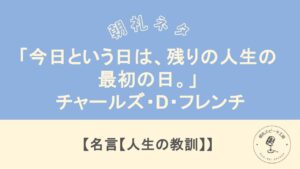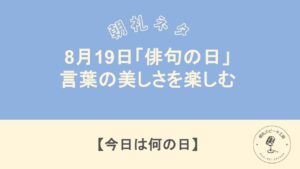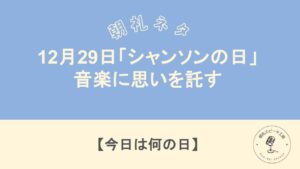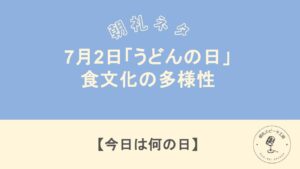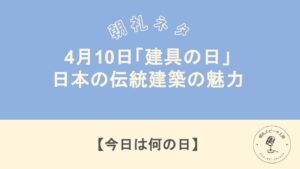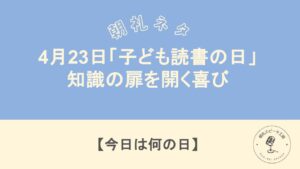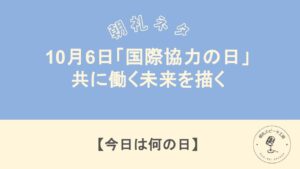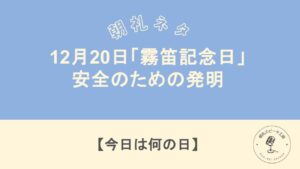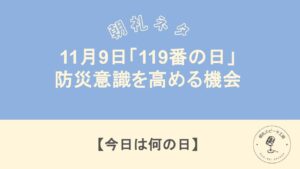目次
1月7日「七草粥の日」:健康を願う日本の伝統
おはようございます。
今日は1月7日、「七草粥の日」です。この日には、春の七草を使った粥を食べ、無病息災を願う日本の伝統があります。今日はこの七草粥の意味や、健康を願う習慣が私たちに与える教訓についてお話しします。
1. 七草粥の由来と意味
七草粥は平安時代から伝わる風習で、無病息災を祈る行事食です。七草とは、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの7種類の野草を指します。これらは、冬場に不足しがちな栄養を補い、疲れた胃腸を休める効果があるとされています。また、お正月のごちそうで疲れた体をリセットする意味も込められています。
2. 健康を願う心の大切さ
七草粥は、健康を願う日本人の想いが形になった伝統的な食文化です。体に良いものを取り入れるだけでなく、自分自身の健康を見つめ直す機会でもあります。忙しい現代生活では、つい食生活が乱れがちですが、七草粥の日に体を気遣う習慣を取り入れることで、日々の健康意識が高まります。
3. 現代に活かす七草粥の教え
七草粥の教えは、現代の生活にも応用できます。例えば、季節の食材を積極的に取り入れることや、体調を気遣う時間を持つことが大切です。さらに、シンプルで栄養豊富な食事を意識することで、心身の健康を保つことができます。七草粥の日をきっかけに、食生活を見直してみるのも良いでしょう。
七草粥は、健康を願うだけでなく、食生活を見直す良い機会です。日本の伝統文化を取り入れながら、心身ともに健やかな一年を過ごしましょう。
今日の七草粥で、無病息災の願いとともに、健康を意識する一歩を踏み出してみてください。
以上です。ありがとうございました。