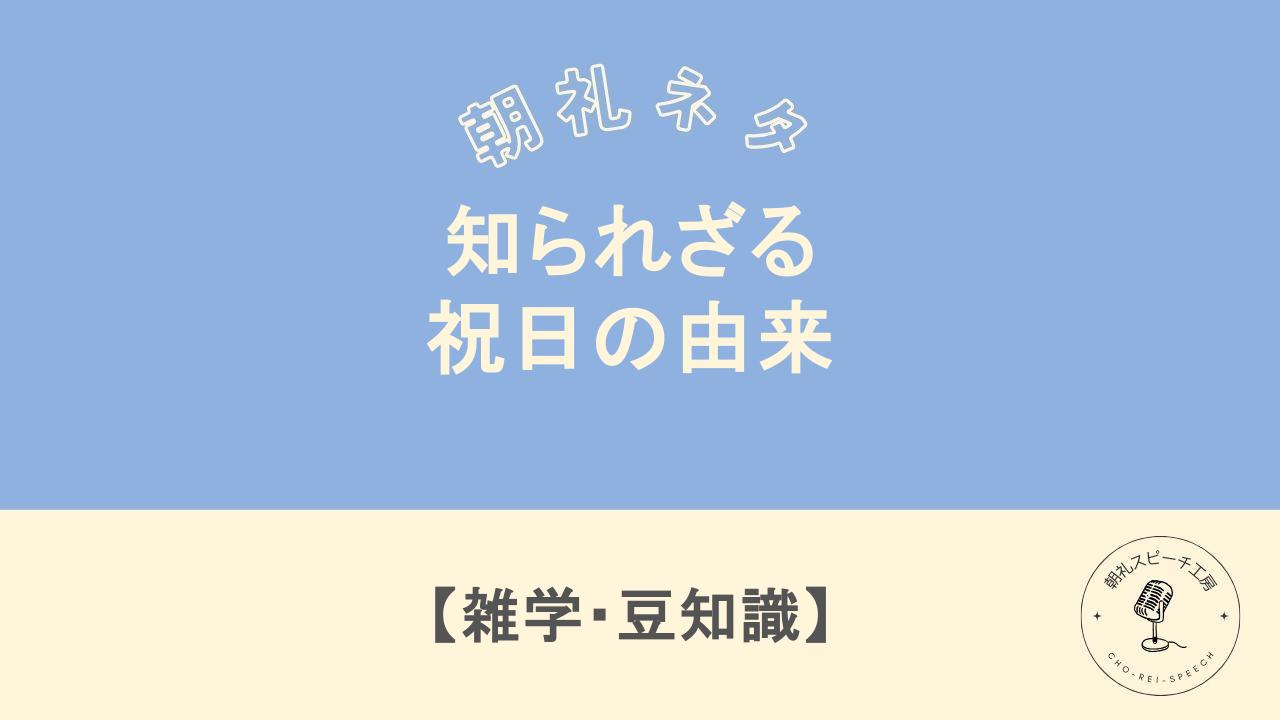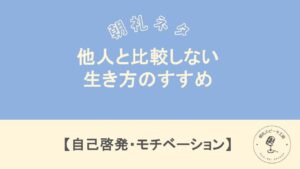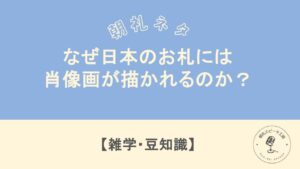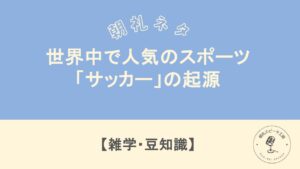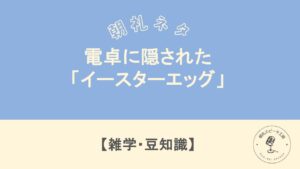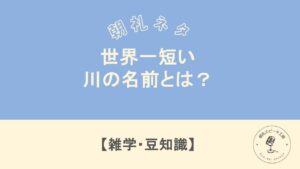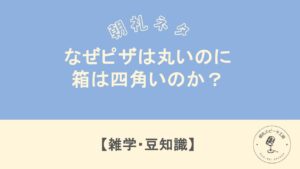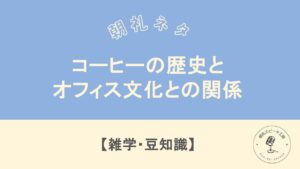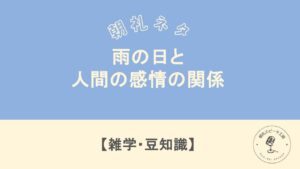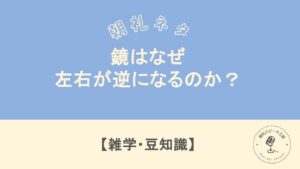目次
知られざる祝日の由来
おはようございます。
普段何気なく過ごしている祝日ですが、その一つひとつに意外と知られていない由来が隠されています。今日は、その中から注目したいポイントを3つご紹介します。
1. 「勤労感謝の日」の農業との関係
毎年11月23日に祝われる「勤労感謝の日」は、もともと「新嘗祭(にいなめさい)」という収穫を祝う行事に由来しています。これは日本古来の文化で、天皇が収穫に感謝を捧げる儀式がルーツです。
2. 「体育の日」から「スポーツの日」への進化
1964年の東京オリンピックを記念して制定された「体育の日」。2020年の東京オリンピックに合わせて「スポーツの日」に改称され、運動を通じた健康や活力の大切さを象徴する祝日として生まれ変わりました。
3. 「憲法記念日」の深い意義
5月3日の「憲法記念日」は、1947年に日本国憲法が施行されたことを記念しています。この日は、平和や民主主義の価値を改めて考える機会として設けられた重要な祝日です。
普段意識せずに過ごしている祝日も、調べてみるとその背景には歴史や文化、社会的な意義が詰まっています。次の祝日を迎えるときには、その由来に少し思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
「祝日の背景を知ると、過ごし方が少し変わります。」「歴史を知ることで、日々の生活に新しい発見を取り入れましょう。」
以上です。ありがとうございました。