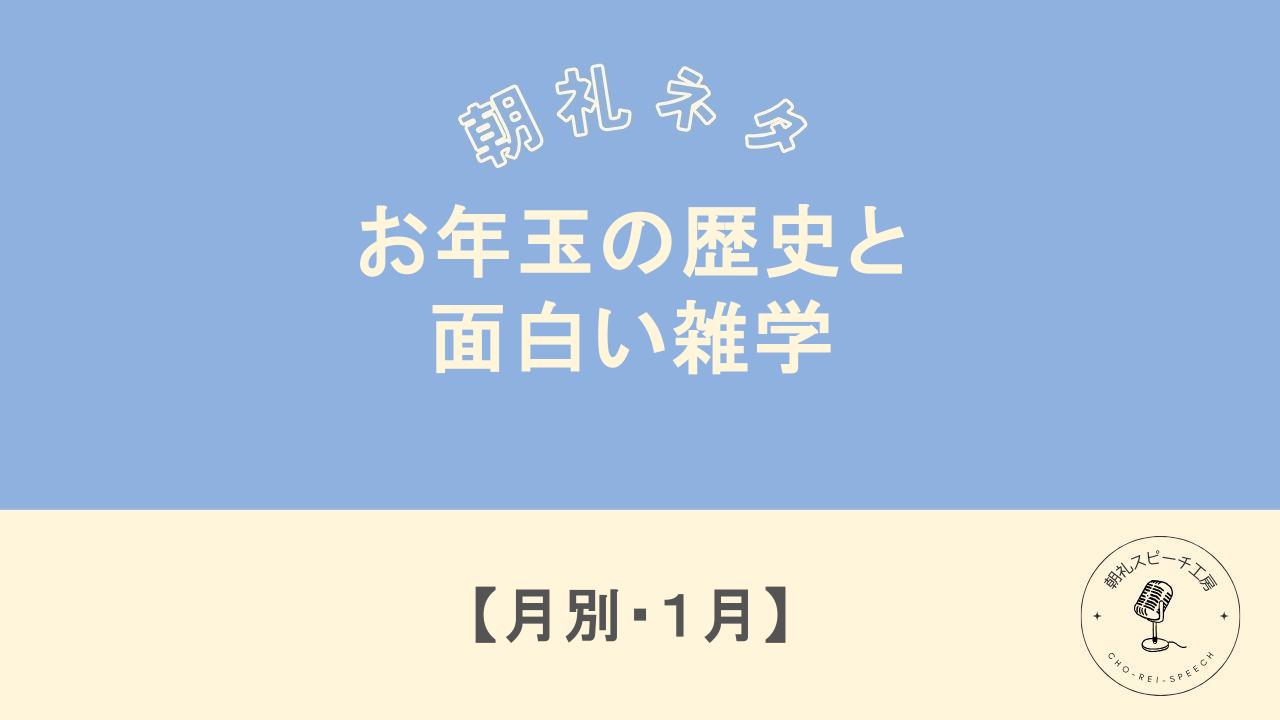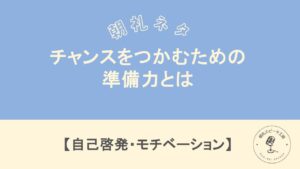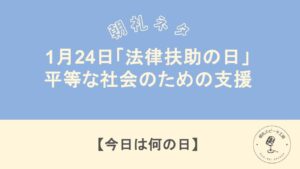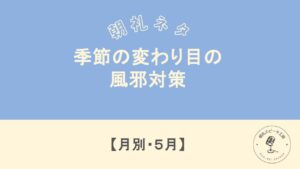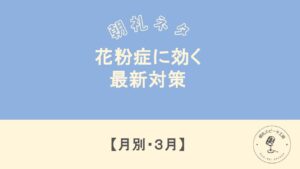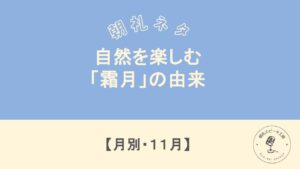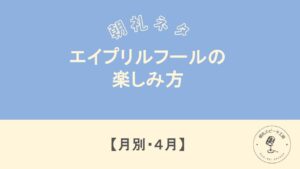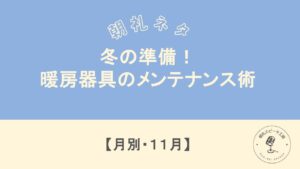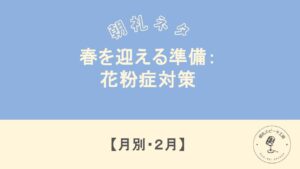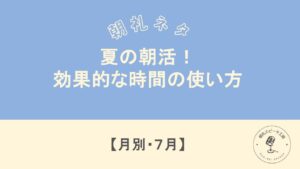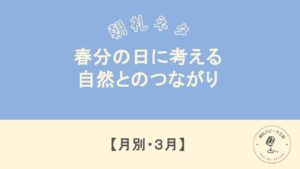目次
お年玉の歴史と面白い雑学
おはようございます。
今日は、皆さんも馴染みのある「お年玉」について、その歴史と少しユニークな雑学をお話ししたいと思います。
1. お年玉の起源
お年玉の起源は、平安時代の「年魂(としだま)」という風習にさかのぼります。この「年魂」は、新年に家長が神様からいただいた魂を家族に分け与える行為でした。これが次第に、金銭や贈り物を渡す形へと変化し、現在の「お年玉」になったのです。
2. 紙幣が使われるようになった理由
江戸時代まではお年玉として主に米や餅が使われていましたが、明治時代に貨幣経済が浸透するにつれ、次第に現金が主流になりました。現在のようにポチ袋に紙幣を入れる形が定着したのは昭和時代になってからです。
3. 世界にも似たような風習がある
日本だけでなく、中国では「紅包(ホンバオ)」と呼ばれる赤い封筒にお金を入れて渡す文化があります。また、韓国では「セベットン」という風習があり、いずれも家族間の絆を深める役割を果たしています。
お年玉は単なる金銭のやり取りではなく、家族の絆や新年の祝福を象徴する大切な文化です。こうした背景を知ると、いつもと違う目でお年玉を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
「お年玉は金額ではなく、心を込めて渡すことが大切です。」ぜひ、この伝統の背景を楽しみながら新年を迎えましょう。
以上です。ありがとうございました。