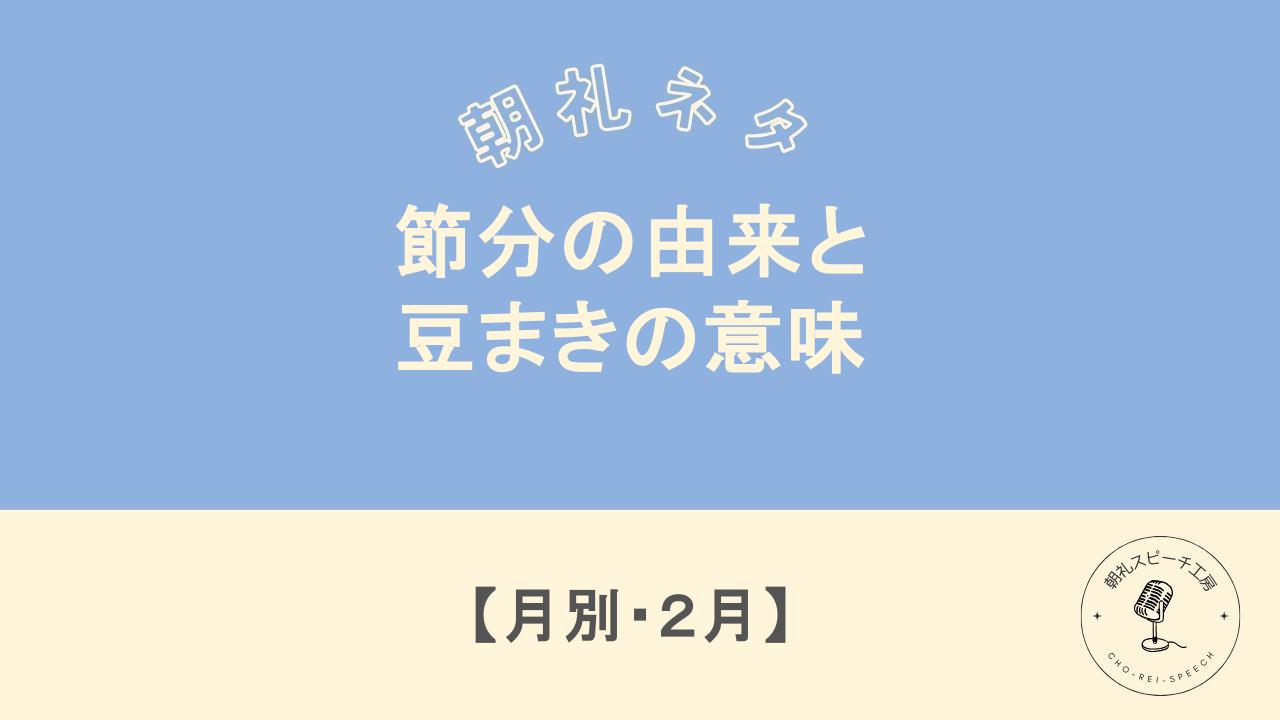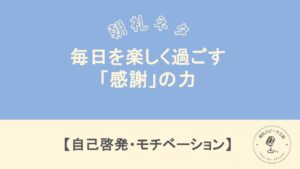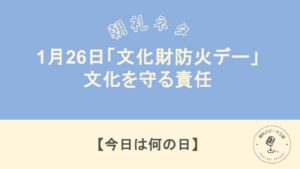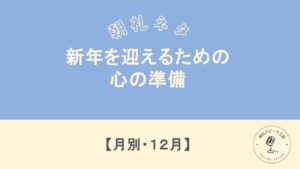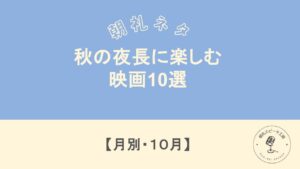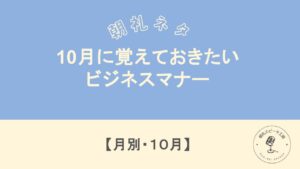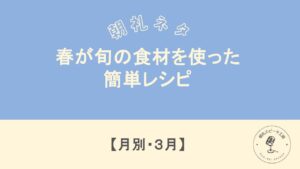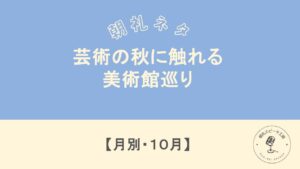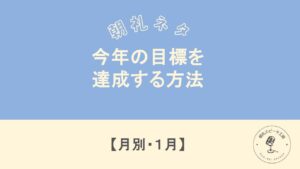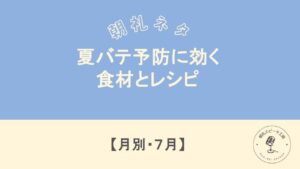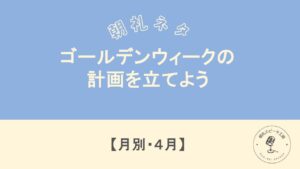目次
節分の由来と豆まきの意味
おはようございます。
もうすぐ節分ですね。この行事は日本の伝統文化の一つですが、由来や意味を知ることで、より深く楽しむことができます。今日は、節分の由来と豆まきに込められた意味をお話しします。
1. 節分の由来
節分とは、もともと「季節を分ける日」を指し、立春、立夏、立秋、立冬の前日すべてを意味していました。しかし、現在では特に「立春の前日」を指すようになりました。立春は一年の始まりとされており、節分には新しい年を迎える準備という意味が込められています。
2. 豆まきの意味
豆まきは、邪気や悪いものを追い払うための風習です。「鬼は外、福は内」と声を出しながら豆を撒くことで、家族の健康や幸せを祈ります。また、「豆」は「魔目(まめ)」を払う、「魔滅(まめつ)」につながる縁起の良いものとされています。
3. 現代における節分の楽しみ方
近年では、豆まきだけでなく、恵方巻きを食べる風習も広がっています。恵方巻きを食べる際に、今年の幸運の方角に向かって願い事をしながら黙々と食べるのも、一つの楽しみ方です。こうした新しい風習も、家族や友人と楽しむ良い機会になりますね。
節分は、一年の健康や幸運を願う日本の大切な文化です。その由来や意味を知ることで、伝統を次世代につなげていく意識が高まります。
「豆を撒くその一粒に、幸せを呼び込む力が宿ります。」今年も節分を通じて、福を呼び込む準備を始めてみませんか?
以上です。ありがとうございました。