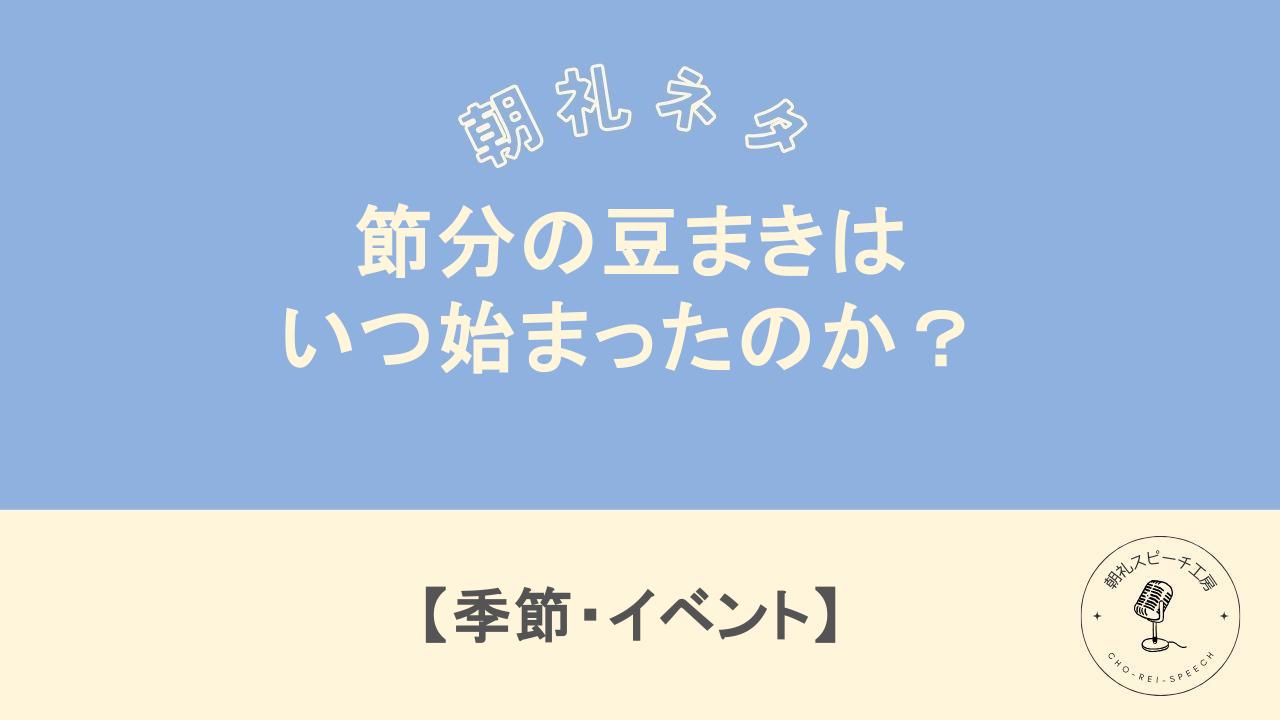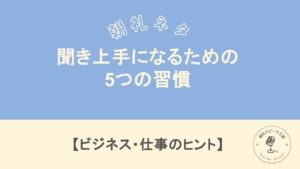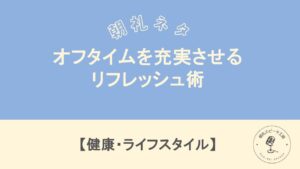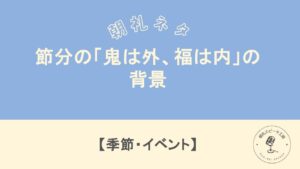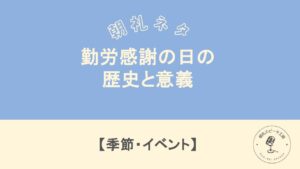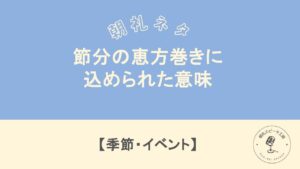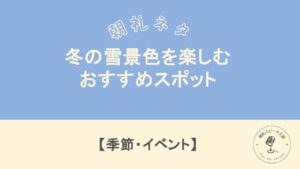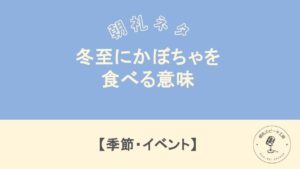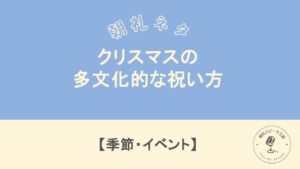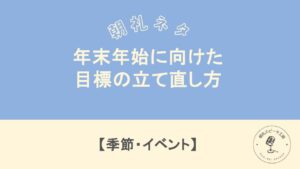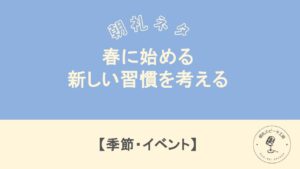目次
節分の豆まきはいつ始まったのか?
おはようございます。
2月の恒例行事といえば「節分の豆まき」です。鬼を追い払うこの風習には、実は長い歴史と意外な背景があります。今日は、節分の豆まきの起源や始まりについて、3つのポイントからお話しします。
1. 節分のルーツは平安時代
節分の起源は、平安時代の宮中行事「追儺(ついな)」にあります。この行事では、悪霊を追い払うために鬼の面を被った人を追い払う儀式が行われていました。当時は豆ではなく、弓矢や呪文が使われていました。
2. 豆まきの由来
豆を使ったのは、鬼=「魔」を滅する、つまり「魔滅(まめ)」という語呂合わせが由来とされています。また、豆には生命力が宿ると信じられ、邪気を払う力があると考えられてきました。この豆まきの風習が広まったのは室町時代ごろとされています。
3. 節分が「家族の行事」に
江戸時代になると、豆まきが庶民の間にも広がり、家族で行う行事として定着しました。豆をまくと同時に「福は内、鬼は外」と唱えることで、家の中の平和や繁栄を祈る意味が込められています。
節分の豆まきは、平安時代の「追儺」にルーツを持ち、室町時代に豆を使った形になり、江戸時代に家族行事として広まりました。現代に受け継がれるこの風習は、長い歴史を感じさせるものです。
「伝統を知ることで、行事がもっと楽しくなります。」今年の節分は、そんな歴史を感じながら豆まきを楽しんでみてください!
以上です。ありがとうございました。