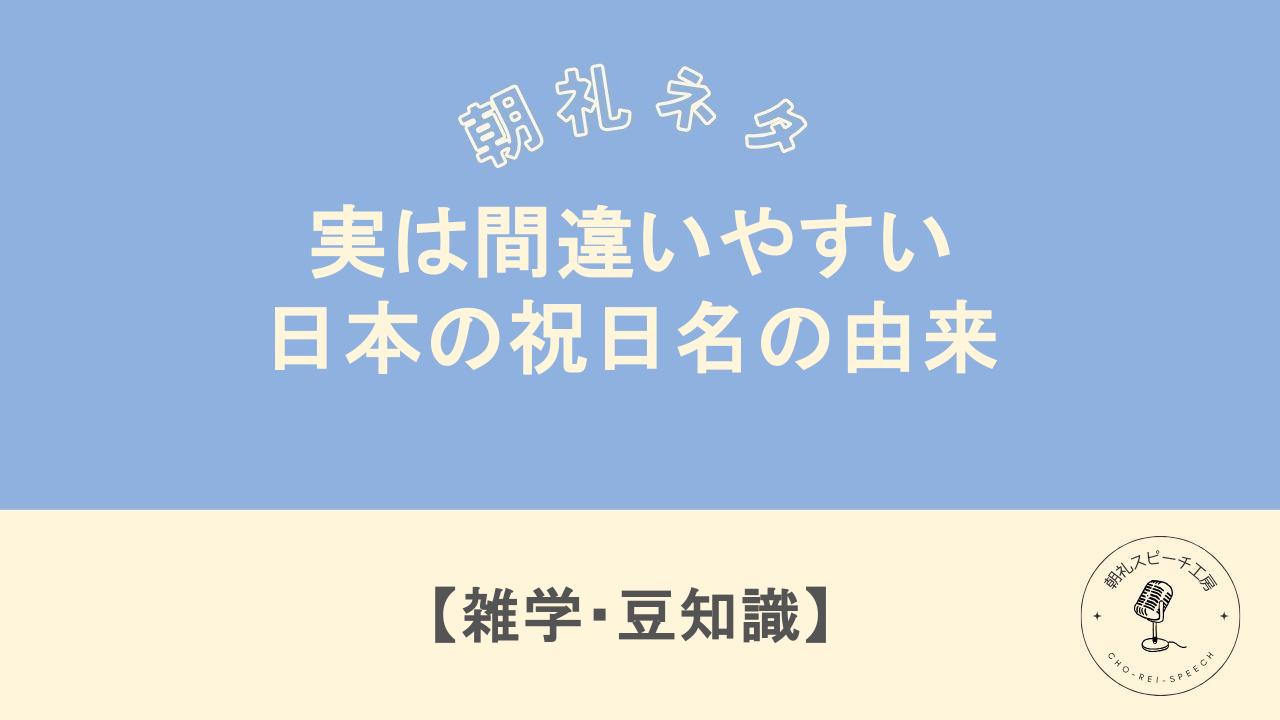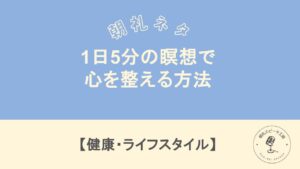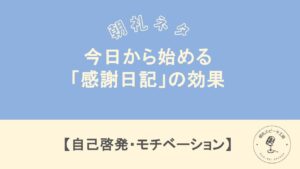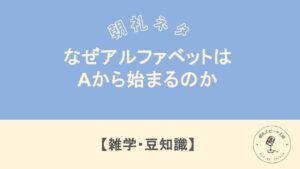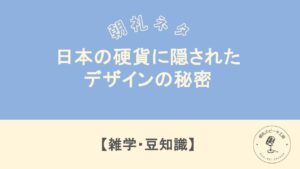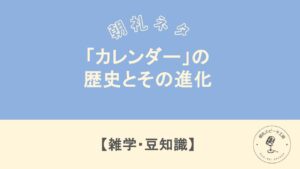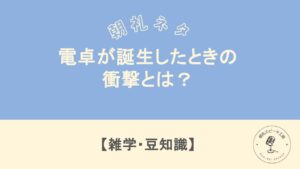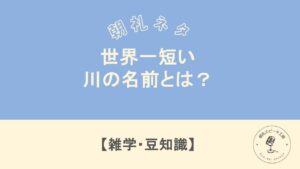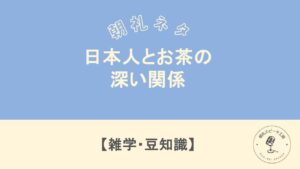目次
実は間違いやすい日本の祝日名の由来
おはようございます。
日本には数多くの祝日がありますが、その名前の意味や由来について正確に理解している人は少ないかもしれません。今日は、間違いやすい日本の祝日名について、由来を3つご紹介します。
1. 勤労感謝の日の「勤労」とは?
11月23日の勤労感謝の日は、「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日」とされていますが、もともとは「新嘗祭(にいなめさい)」という五穀豊穣を祝う伝統行事がルーツです。そのため、勤労感謝の日は働くことだけでなく、自然の恵みに感謝する意味も込められています。
2. 建国記念の日の「記念の日」とは?
2月11日の「建国記念の日」は、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」とされています。しかし、実際に「建国の日」ではなく「記念の日」と表記されているのは、日本の建国が具体的にいつかを歴史的に確定できないため、祝日の名前に柔軟性を持たせた結果です。
3. 海の日と山の日、どちらが先?
夏の祝日である「海の日」は7月に、そして比較的新しい「山の日」は8月に設定されています。「海の日」は、1876年に明治天皇が灯台視察のために船で巡行した記念日を起源としており、一方の「山の日」は、山に親しむ機会を増やし、その恩恵に感謝する目的で2016年に新設されました。山の日は祝日の中で最も新しいものです。
日本の祝日はそれぞれ深い歴史や意味が込められています。勤労感謝の日、建国記念の日、海の日と山の日の由来を知ることで、ただの「休みの日」ではない特別さを感じられますね。
「祝日の由来を知ることが、日々の感謝や文化の理解につながる。」次の祝日には、ぜひその意味を考えてみてください。
以上です。ありがとうございました。