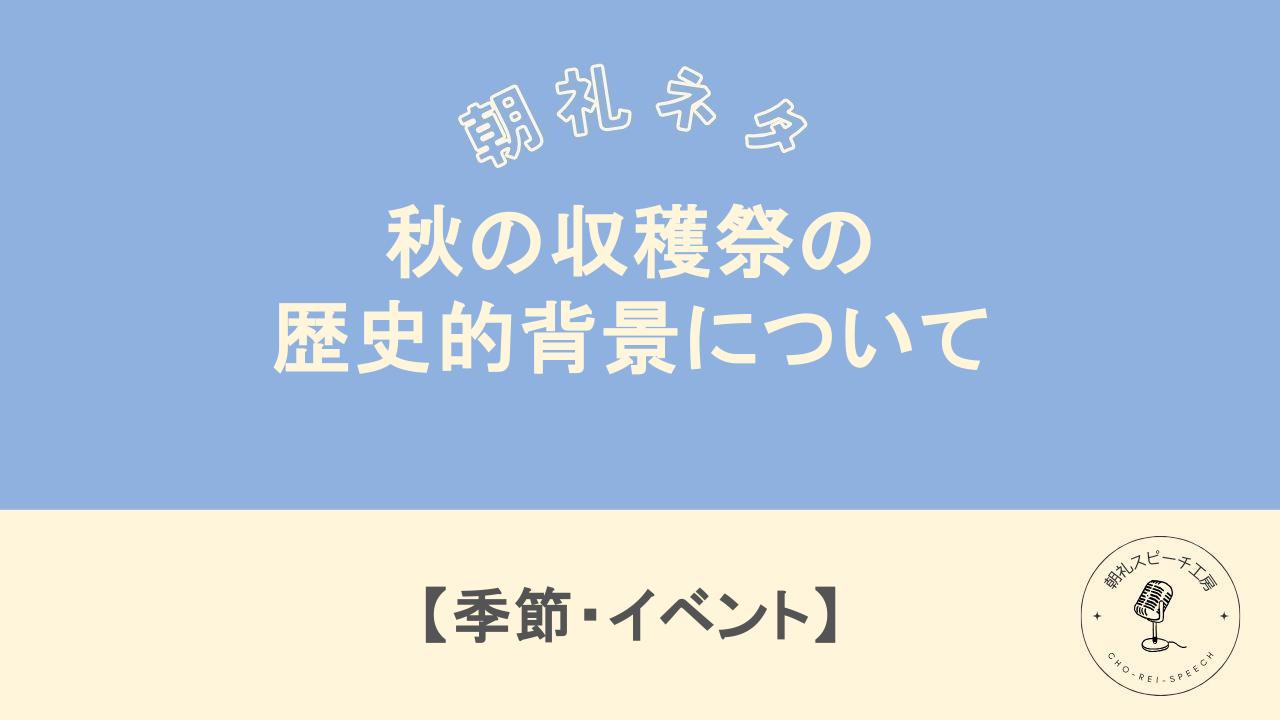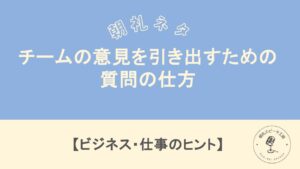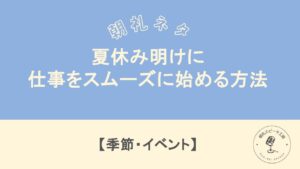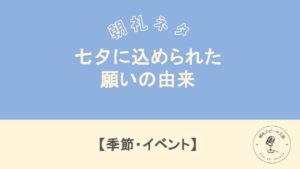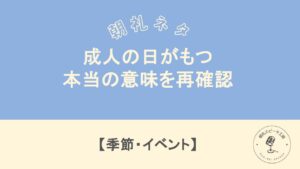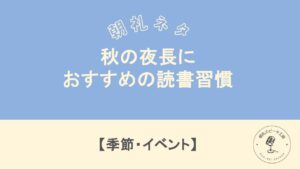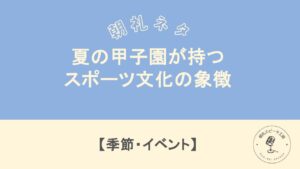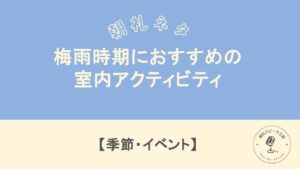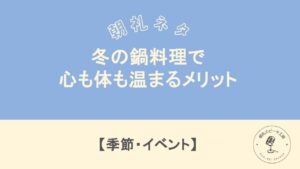目次
秋の収穫祭の歴史的背景について
おはようございます。
秋といえば、収穫の季節ですね。全国各地で行われる収穫祭には、地域ならではの伝統や文化が込められています。でも、これらの収穫祭にはどのような歴史的背景があるのでしょうか?今日はそのポイントを3つにまとめてお話しします。
1. 収穫祭の起源は感謝の儀式
収穫祭の歴史は、農業が始まった古代にまで遡ります。収穫の成功を神々や自然に感謝し、翌年の豊作を祈る儀式として行われたのが始まりです。
2. 日本独自の収穫行事
日本では「新嘗祭(にいなめさい)」が古代から行われています。天皇が新米を神々に捧げるこの行事は、現在の「勤労感謝の日」にも影響を与えています。地域ごとに異なる祭りも多く、伝統文化として大切にされています。
3. 現代の収穫祭への変化
現代では、収穫祭は地域活性化や観光イベントとしての側面が強くなっています。地元の特産物をアピールしたり、地域の絆を深めたりと、新たな形でその役割を果たしています。
秋の収穫祭には、感謝の気持ちを伝えるという普遍的な価値が込められています。その歴史を知ることで、祭りをより深く楽しむことができますね。
「収穫祭は、過去と未来をつなぐ感謝の祭りです!」
以上です。ありがとうございました。