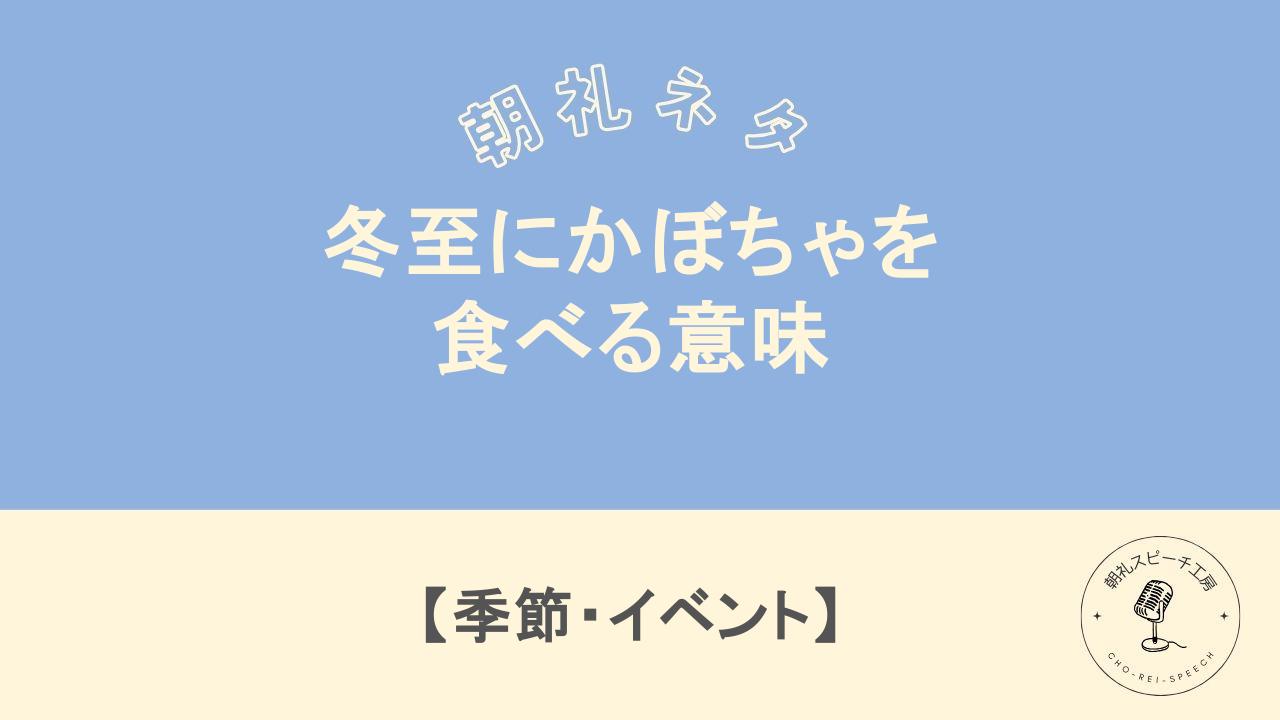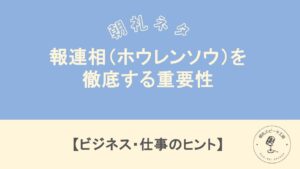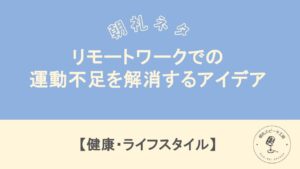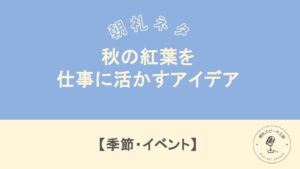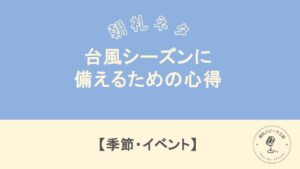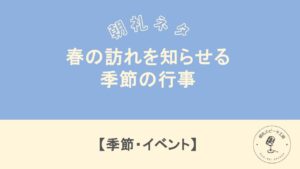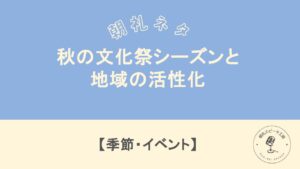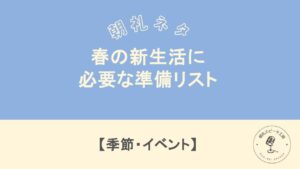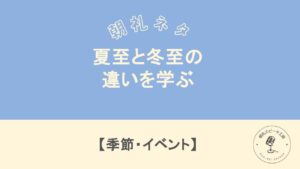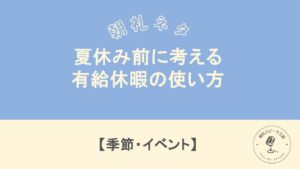目次
冬至にかぼちゃを食べる意味
おはようございます。
冬至にかぼちゃを食べる風習は、昔から日本で親しまれています。本日は、この風習に隠された意味を3つのポイントでご紹介します。
1. 栄養補給と健康祈願
かぼちゃは栄養価が高く、特に冬に不足しがちなビタミンAやカロテンが豊富です。冬至の日にかぼちゃを食べて体を温め、風邪を引かないようにとの願いが込められています。
2. 太陽の力を取り入れる象徴
冬至は1年で最も夜が長い日です。この日を境に日が少しずつ長くなっていくことから、「太陽が再び力を取り戻す日」とされています。太陽に似た丸い形や黄色い色のかぼちゃは、太陽のエネルギーを象徴する食べ物とされているのです。
3. 食料保存の知恵から生まれた風習
昔の日本では、冬に保存できる食材が限られていました。かぼちゃは長期間保存できるため、冬至に食べることで冬の厳しい時期を乗り越えようとした先人たちの知恵が反映されています。
冬至にかぼちゃを食べるのは、健康と太陽の力を取り入れるための象徴的な行為です。古くから続くこの風習を味わいながら、冬の始まりを乗り越える準備を整えましょう!
「冬至にはかぼちゃを食べて、元気に冬を迎えましょう!」
以上です。ありがとうございました。