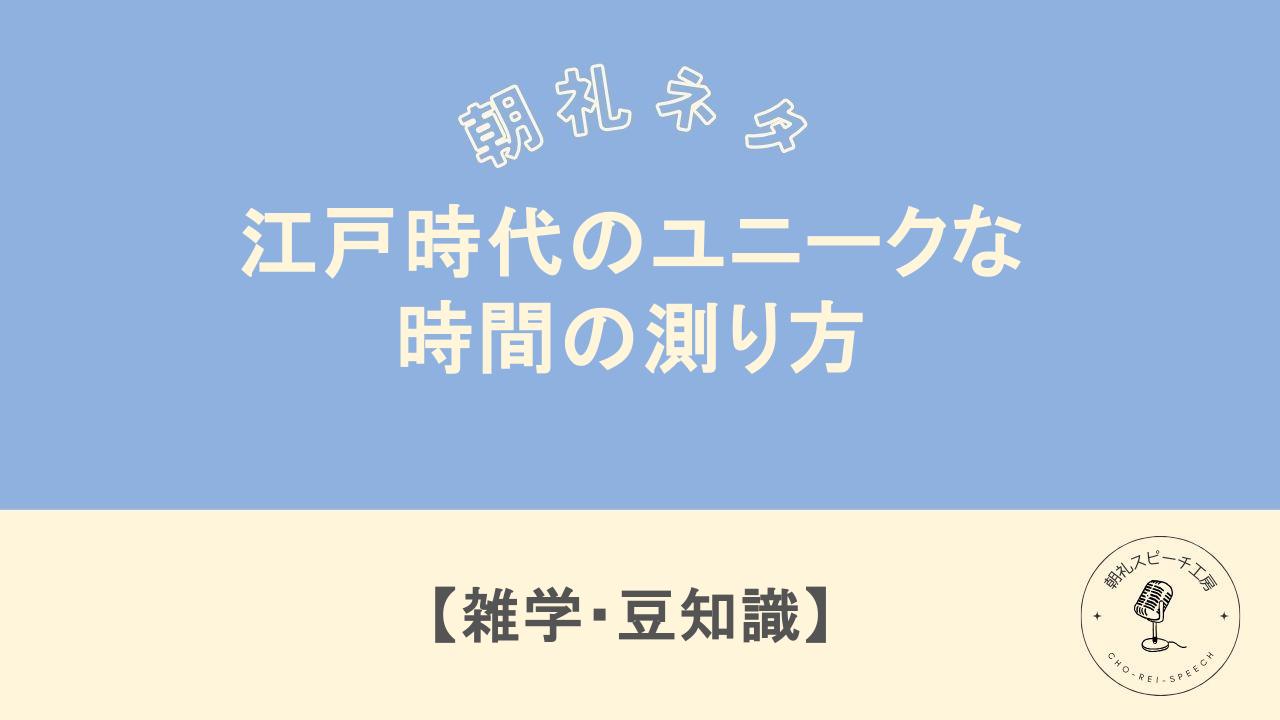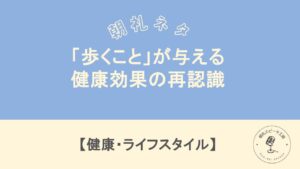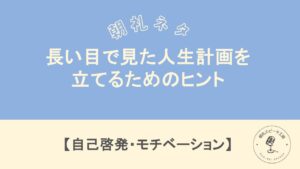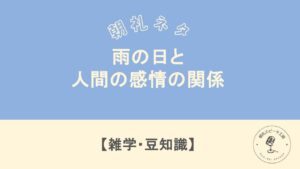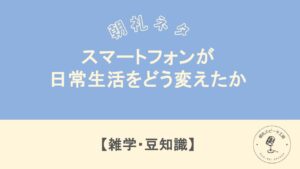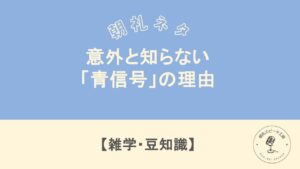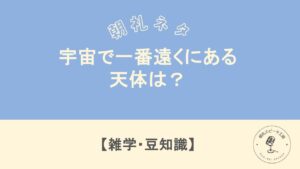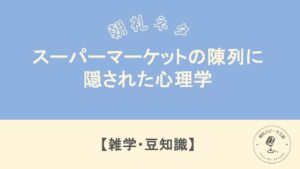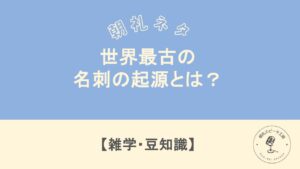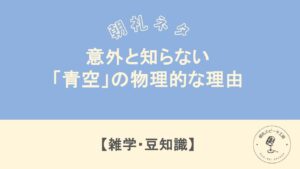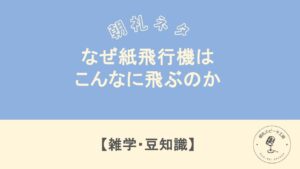目次
江戸時代のユニークな時間の測り方
おはようございます。
今日は、現代の時間の感覚とは全く異なる、江戸時代の「ユニークな時間の測り方」についてお話しします。歴史を少し振り返りながら、3つのポイントに分けてご紹介します。
1. 不定時法とは?
江戸時代には「不定時法」という独自の時間の測り方が使われていました。一日を昼と夜に分け、それぞれを6等分する方法です。そのため、夏は昼が長く、夜が短い時間配分になり、冬はその逆になります。自然のリズムに合わせた柔軟な時間感覚が特徴的です。
2. 時間を知らせる「時の鐘」
時計が一般的でなかった時代、時間を知らせるために使われたのが「時の鐘」です。各地の寺院で決まった時刻に鐘を鳴らし、人々はその音を聞いて生活のリズムを整えていました。現代でいう公共の時計のような役割を果たしていたのです。
3. 長さを基準にした時間の測り方
面白いのは、時間の単位を「燃えるお香の長さ」や「ロウソクの燃焼時間」で測っていたことです。たとえば、特定の長さのお香が燃え尽きるまでを「一刻」としていたのです。手作りの道具を使いながら、当時の人々は工夫して時間を管理していました。
江戸時代には、自然のリズムに合わせた不定時法、時の鐘、そしてお香やロウソクを使った時間管理など、ユニークな方法で時間を測っていました。これらは現代の効率性重視とは異なり、時代背景に合わせた実用的で柔軟な工夫の結晶です。
江戸時代の時間の測り方から学べるのは、自然に寄り添いながら自分らしいペースで生きる大切さです。私たちも、忙しさの中で少しだけ「柔らかい時間感覚」を取り入れてみませんか?
以上です。ありがとうございました。